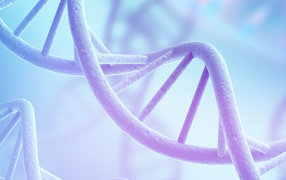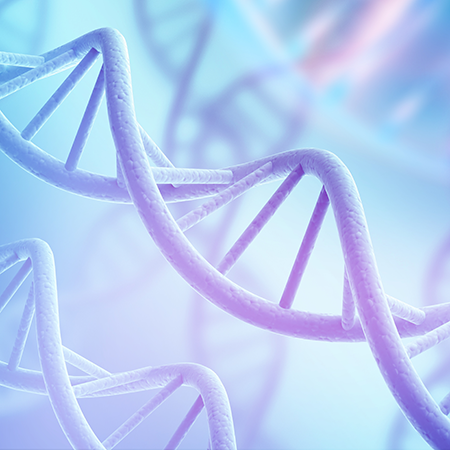
脊髄性筋萎縮症(SMA)は出生児1万人に1人の割合で発症する遺伝性疾患で、進行性の筋力低下を引き起こします。この疾患に対する新たな治療戦略が、医学界で大きな注目を集めています。
2025年にNew England Journal of Medicine(NEJM)に掲載されたFinkelらの論文 (DOI:10.1056/NEJMc2300802) では、SMAに対する胎児期の治療効果が報告されました。この研究では、SMAを持つ女児の母親が妊娠後期に遺伝子標的薬「リスジプラム(Risdiplam)」を服用し、出生後も女児の治療を継続しました。その結果、女児は2歳半になった現在も症状が現れていないと報告されています。
この画期的な研究に対し、Nature誌のNews欄でも絶賛されており、胎児期からの治療がSMAの症状発現を抑える可能性を示した点が高く評価されています。
今回の報告は、NEJMではCorrespondence(短報)として掲載されました。通常、NEJMのような権威ある医学誌では、ランダム化比較試験などの大規模研究が多く掲載されます。しかし、本症例のように科学的・臨床的インパクトが極めて大きい場合、単独の症例報告であってもトップジャーナルに掲載されることがあるという好例と言えるでしょう。
胎児期からのSMA治療は、今後の神経筋疾患治療のパラダイムを変える可能性があります。さらなる研究が進むことで、このアプローチが標準治療となる日も近いかもしれません。
このように、胎児期から遺伝性疾患を治療できる可能性が広がることで、着床前遺伝学的検査(PGT-M)に関する議論も変わってくるかもしれません。PGT-Mは、特定の遺伝疾患を持たない受精卵を選択するための技術ですが、もし出生後や胎児期に効果的な治療が確立されれば、疾患を持つ受精卵でも健康な人生を送れる可能性が出てきます。
遺伝性疾患のリスクを回避するためにPGT-Mが検討される疾患に関して、今後は「疾患があっても治療で健康に成長できるならば、PGT-Mの必要性はどう変わるのか?」といった倫理的・医学的な議論がより深まるでしょう。
胎児期からのSMA治療は、今後の神経筋疾患治療のパラダイムを変える可能性があります。さらなる研究が進むことで、このアプローチが標準治療となる日も近いかもしれません。そして、それに伴い、生殖医療の選択肢や考え方も変化していくことが予想されます。