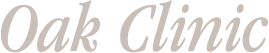
日本産科婦人科学会では、22週(赤ちゃんがお母さんのお腹の外では生きていけない週数)より前に妊娠が終わることを「流産」と定義しています。
妊娠の15%前後が流産という統計もあり、誰にでも起こりうることです。
中でも流産の約80%は妊娠12週までに起こる早期流産です。
流産の原因は、原因不明の場合も多いですが、原因が明らかになったものについては、胎児側の要因と母体側の要因に分けることができます。
胎児側の要因のほとんどは染色体異常です。
染色体異常のある受精卵の多くは着床しても、発育が途中で止まってしまいます。
実際に流産になった胎児の染色体を調べてみると、65%に異常が見つかります。
また、母体が35歳を超えると、染色体異常の見つかる胎児は74%に増加します。
母体側の要因としては、免疫や凝固因子の異常、子宮の異常などがあります。
免疫の異常としては「抗リン脂質抗体症候群」、凝固因子の異常としては、血液凝固の第Ⅻ因子の低下が関連しているといわれています。
子宮の異常は、子宮内膜が炎症を起こし、内膜の組織同士がくっついてしまった「子宮内腔の癒着」や子宮の中に仕切りのある中隔子宮、子宮の上部がハート型のようにくびれた双角子宮といった「子宮形態異常」などです。
流産をしてしまうと、「原因が自分にあるのでは」と自分の生活や仕事などを振り返って自分を責めてしまう方がおられます。
しかし、流産の原因が妊婦さんの生活や仕事であることはほとんどありません。
2回以上の連続した流産を「反復流産」、3回以上連続して胎児心拍を確認した流産の場合を「習慣流産」と言います。
同時に、妊娠してもおなかの赤ちゃんが育たず、流産や死産を繰り返してしまう状態を「不育症」といいます。
流産のほとんどの原因は、胎児の染色体異常、自然淘汰による自然流産です。
しかし、3回以上流産を繰り返す流産では、何か流産を起こしやすいリスク因子があるかどうかを検査する必要があります。
リスク因子がある場合でも、100%流産するわけではありません。
不育症のリスク因子には、夫婦どちらかの均衡型転座などの染色体構造異常があります。
この場合、夫婦とも全く健康ですが卵や精子ができる際(染色体が半分となる減数分裂の場合)、染色体に過不足が生じることがあり、流産の原因となります。
また、妻側のリスク因子として、子宮形態異常、内分泌異常、凝固異常、母体の高齢年齢などがあります。
着床前診断の一般的な情報を提供しています。